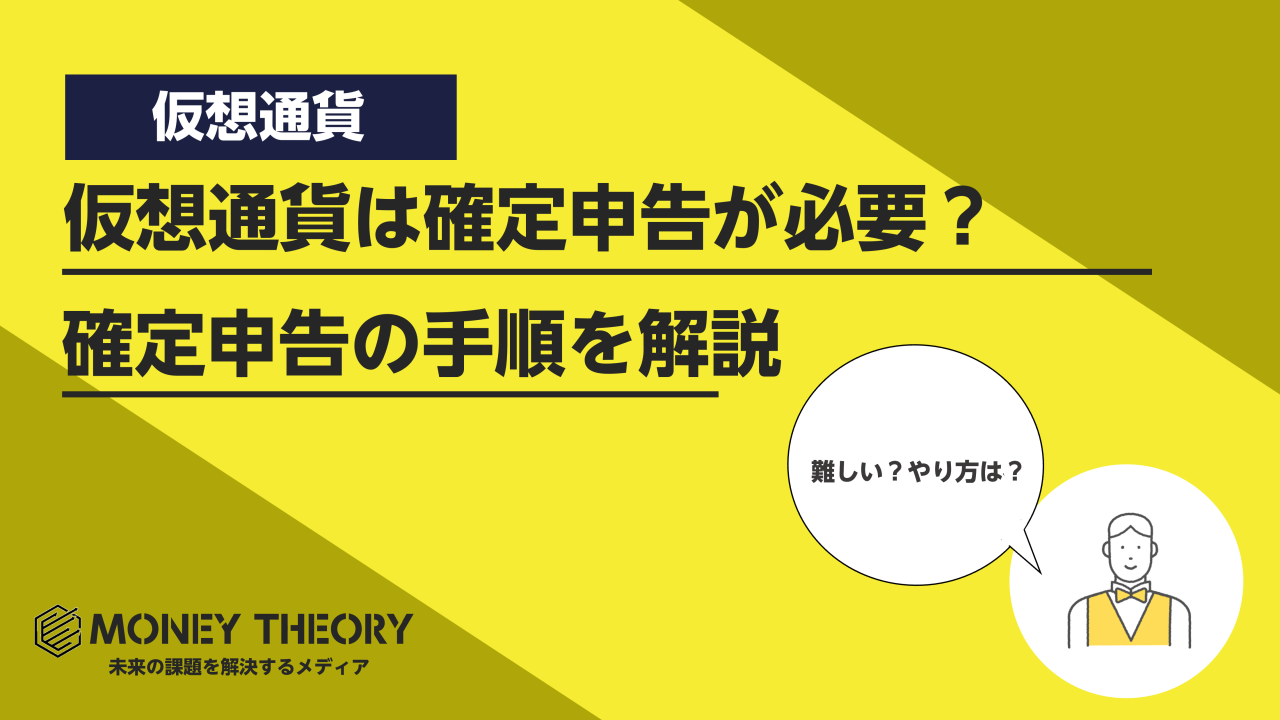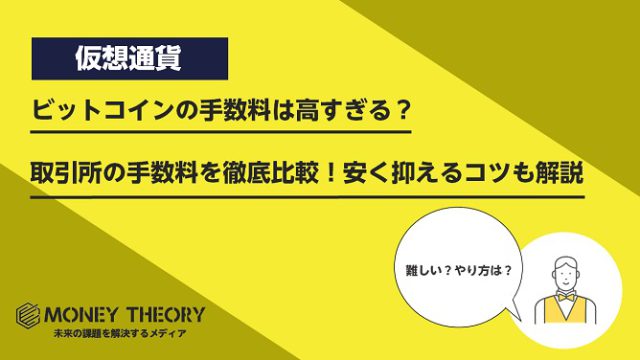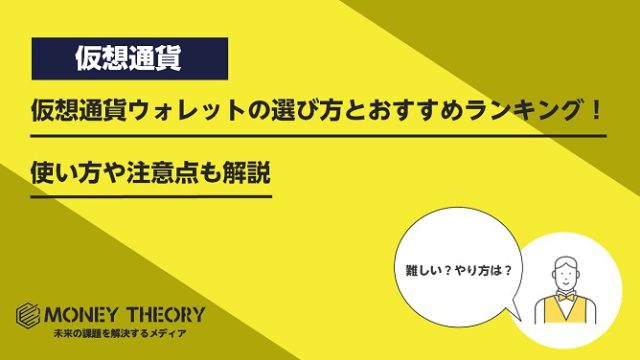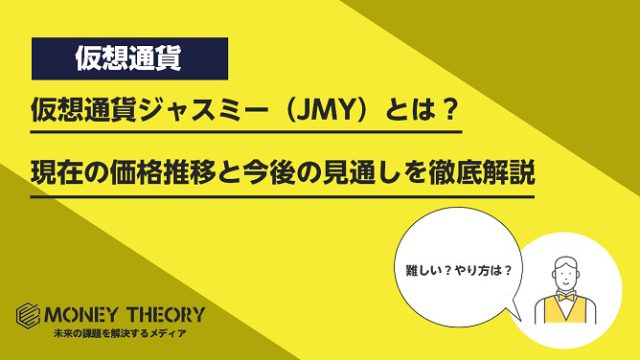「仮想通貨取引は確定申告が必要?」
「税金額はどのように計算される?」
仮想通貨取引をしている人は、以上のように税金について悩んでいる人も多いはずです。
結論から言えば、仮想通貨取引で利益を出した場合、確定申告をして税金を納める必要があります。
この記事では仮想通貨取引で確定申告をする必要があるケースを紹介して、税金額の計算方法や確定申告の手順を解説します。
ビットコイン(仮想通貨)にかかる税金は? 所得に応じた税率や確定申告の方法を解説
仮想通貨取引で利益が出ると確定申告が必要

ビットコインやアルトコインなどの仮想通貨取引では、一定以上の所得を出すと確定申告をする必要があります。
確定申告が必要になる所得額は、会社員など給与所得を得ているか、学生・主婦などの扶養家族かどうかによって次のように変わります。
| 区分 | 所得 |
|---|---|
| 会社員 | 20万円以上 |
| 学生や主婦など扶養家族 | 33万円以上 |
20万円は基礎控除額、33万円は住民税の基礎控除額なので、それ以下の所得であれば確定申告をする必要はありません。
またフリーランス・個人事業主の人は金額に関わらず確定申告が必要です。
アルトコインのおすすめ7選!今後の見通しと将来性のあるコインを徹底解説
仮想通貨は雑所得に含まれる
仮想通貨取引で得た所得は、雑所得として総合課税の対象になります。
総合課税は給与所得と合算した金額で税率が決まります。
例えば年収500万円の会社員であれば、課税所得は約370万円ですが、仮想通貨取引で50万円の利益を出せば所得合計約420万円の総合課税となります。
仮想通貨取引は次の表のように累進課税をかけられるため、20%の税率が適用されます。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
累進課税制度は収入が増えれば最大で45%、住民税の10%と合わせると55%の税率がかけられます。
イーサリアム(ETH)の今後の見通しは?価格変動の要因と価格予想を徹底分析
仮想通貨の確定申告をしないと延滞税と加算税が追加でかかる
仮想通貨取引の確定申告をしないと、延滞税と加算税が追加でかかります。
延滞税は、申告期限の翌日から納付した日までの日数によって、最大14.6%の年利をプラスした金額を納める必要があります。
また加算税は次の二種類の場合によって課せられる年利が変わります。
過少申告加算税【最大15%】:申告額が正しい額より少なかった場合
無申告加算税【最大30%】:申告遅れや申告忘れの場合
他にも故意で申告額の誤魔化しや無申告の場合は「重加算税」として最大50%の利率が課せられるので気をつけましょう。
税務署は取引所に対して取引情報の開示を求めることができるので、税金を納めなければ間違いなくペナルティを受けることになります。
仮想通貨取引で利益を出している場合、利益を計算して確定申告が必要か確認しておきましょう。
仮想通貨取引で所得が発生するタイミング
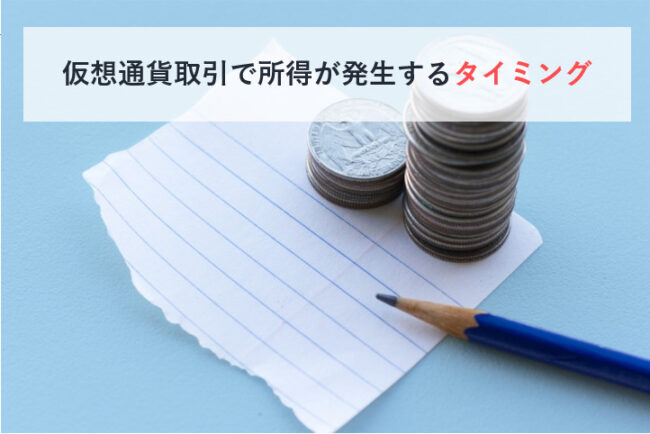
仮想通貨取引で所得が発生するタイミングは次の3つのタイミングです。
- 仮想通貨を売却したとき
- 仮想通貨を決済したとき
- 仮想通貨を他の仮想通貨取引に利用したとき
仮想通貨取引は保有しているタイミングではなく、取引が完了した時点で利益が確定します。
以下にそれぞれのタイミングを解説します。
仮想通貨を売却したとき
保有していた仮想通貨を売却して利益が出た際は、所得が発生します。
仮想通貨を保有しているだけでは、どれだけ含み益が出たとしても所得には換算されず、売却した時点で所得が発生します。
仮想通貨取引における利益の計算方法は、売却時の価額と取得時の価額の差し引きで計算できます。
取引手数料などの経費も合わせて計算するため、売却時に得た利益額がそのまま所得として計算するだけで構いません。
仮想通貨を決済した時
仮想通貨で決済した場合も、所得が発生したとみなされます。
仮想通貨で決算する場合、直接仮想通貨で払うことはできず、いったん日本円に売却してから商品を購入する取引となるからです。
仮想通貨をいったん売却して日本円に替えているため、前述した売却時と同じように仮想通貨の所得が発生することになります。
仮想通貨で決済をするだけで所得の対象にされるため、税金額を減らしたい場合はあまり決済するべきではありません。
また仮想通貨で商品を購入していただけで課税対象になるケースもあるので、見落としのないように気をつけましょう。
仮想通貨を他の仮想通貨取引に利用した時
仮想通貨を別の仮想通貨を交換する取引も、同じく所得が発生します。
前述した決済しただけで所得が発生するのと同じく、仮想通貨を売却して日本円に換えた後、新たに他の仮想通貨を購入したとみなされるからです。
仮想通貨同士の取引や決済は、利益が発生していないため課税対象にならないと間違える可能性が高いです。
仮想通貨は何もせずに保有し続ける以外の取引では所得が発生すると覚えておきましょう。
仮想通貨で利益を出した際の税金計算方法
仮想通貨取引で会社員であれば20万円以上の所得を出した場合、確定申告をする必要があります。
仮想通貨の税金計算方法は、次の2つの方法がとられます。
- 移動平均法
- 総平均法
どちらの計算方法でも課税される金額は同じですが、一度選択すると3年間は変更できないため注意が必要です。
また、総平均法であれば一括で変更できるため、個人で仮想通貨取引を行っている場合は総平均法で計算するのがおすすめです。
以下にそれぞれの計算方法を分かりやすく解説します。
移動平均法
移動平均法とは、仮想通貨を購入したごとに取得価額と残高の平均を出して、所得を計算する所得計算方法です。
仮想通貨を購入するたびに「購入した金額の合計÷数量=取得価格」を計算するため、年の途中でもおおよその見積もりがだしやすいメリットがあります。
しかし、スキャルピングやデイトレードのように取引回数が多い場合、毎回計算していると多大な計算回数になるため総平均法を利用した方が良いこともあります。
総平均法
総平均法は、1年間に購入した金額の合計を数量の合計で割って、取得価額(単価)をまとめて計算する方法です。
取引事業者によって発行された年間取引報告書を国税庁が用意する計算書に転記すれば自動で計算できるため、個人投資家でも楽に計算できるメリットがあります。
ただし、移動平均法のように年途中で所得計算がしづらいため、税金がいくら程度になるか予測しづらいデメリットもあります。
会社員として働きながら仮想通貨取引をしている個人投資家の場合は、総平均法でまとめて計算する総平均法をおすすめします。
仮想通貨トロンの見通しは?価格変動の要因から今後の推移を徹底分析
仮想通貨の確定申告の手順
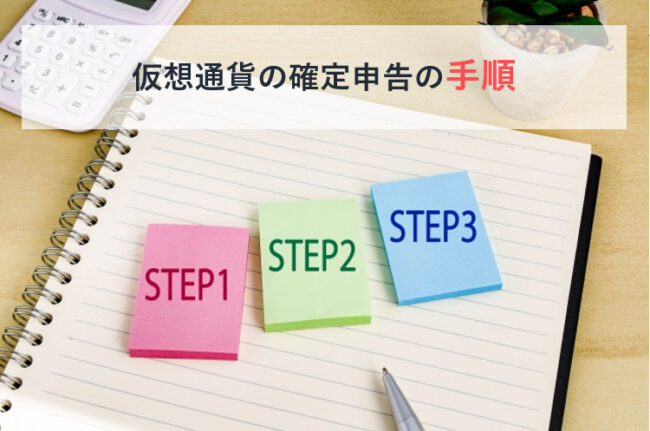
仮想通貨の確定申告の流れは次の通りです。
- 仮想通貨交換業者から「年間取引報告書」の交付を受ける
- 「仮想通貨の計算書」を作成する
- 確定申告書を作成する
現在は税務署にわざわざ足を運ぶ必要はなく、ネット上で申請すれば確定申告ができます。
そのため、必要書類を準備してから、できるだけ早い段階で確定申告を行いましょう。
以下にそれぞれのステップごとに解説していきます。
仮想通貨交換業者から「年間取引報告書」の交付を受ける
まずは仮想通貨交換業者から「年間取引報告書」の交付を受けて、自分の所得額を知りましょう。
年間取引報告書は大抵1月末~2月頭に仮想通貨取引所から全員に交付されるので、特に申請する必要はありません。
交付された年間取引報告書に記載されている所得金額が20万円を越えている場合は、確定申告を行う必要があります。
確定申告時に資料として必要なだけなので保存しておく必要はありませんが、万が一税務調査が入った場合は取引所の取引データ開示を求められることもあります。
確定申告の際に使用した取引データは大切に保存しておきましょう。
「仮想通貨の計算書」を作成する
年間取引報告書の内容を用いて、国税庁が公開している仮想通貨の計算書に入力します。
仮想通貨の計算書に内容を入力すれば、申告に必要な所得金額等を自動計算してくれるため、個人で計算しなおす必要はありません。
ちなみに、計算方法は総平均法で計算されます。
移動平均法で計算する場合、自信でエクセルの表などを作成して計算する必要があるので気をつけましょう。
確定申告書を作成する
確定申告に必要な金額が計算できれば、ついに確定申告書を作成します。
確定申告は国税庁の「確定申告書作成コーナー」から、パソコン・スマホどちらからでも申請できます。
ネット上で確定申告を行う場合、計算した所得金額の計算書に加えて次の書類を準備しておくとスムーズに申請可能です。
- マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)
- 還付金を受け取る口座番号が記載された通帳
- 社会保険料や生命保険料の支払額証明書
- 医療費控除を受けるなら医療費の明細書
- 寄附金控除を受けるなら寄附金受領証明書
また仮想通貨取引で得た所得は雑所得の部分に記載することになるので、間違えないように注意しましょう。
ビットコインの少額投資では儲からない? 少額でできる取引方法と儲けるコツを徹底解説
仮想通貨取引の申告に関する注意点
仮想通貨取引の確定申告に関する注意点を解説します。
- 損益通算できない
- 総合課税の対象となる
- 仮想通貨の種類ごとに評価方法を設定する必要がある
損益通算できない
仮想通貨取引においては、利益と損失を通算して計算する「損益通算」ができません。
つまり、個別の取引ごとに利益と損失を計算し、それぞれの金額を申告する必要があります。
取引履歴や取引所の記録を元に正確に計算しましょう。
総合課税の対象となる
仮想通貨取引で得た利益は、他の所得と合算して総合課税の対象となります。
つまり、給与所得や事業所得など他の所得と一緒に計算され、所得税や住民税が課税されます。
取引の利益が一定の金額を超える場合は、確定申告が必要です。
仮想通貨の種類ごとに評価方法を設定する必要がある
仮想通貨の評価方法は、通貨の種類ごとに異なります。
一般的には、評価基準日の時点での相場価格を基準にして評価します。ただし、一部の通貨では他の評価方法が採用されることもあります。
正確な評価額を設定するために、取引所や公式情報源のデータを活用しましょう。
仮想通貨取引でできる節税対策
仮想通貨取引は雑所得として計算されるため、納める税金が高額になる可能性があります。
しかし、節税方法としては次の内容があります。
- 仮想通貨の収益を得るための費用を必要経費とする
- 別の仮想通貨と損益通算する
- 海外の為替FXの損失と相殺
上記の方法を取るには毎年確定申告をする必要がありますが、節税をすることで納税額を減らすことができるため面倒でもしておいた方がお得です。
以下にそれぞれの方法を解説します。
仮想通貨取引の費用を必要経費とする
仮想通貨取引に用いた費用を必要経費とすることで、所得を抑えることができます。
仮想通貨取引における「所得」とは、得た利益から仮想通貨取引で使った費用を差し引いた金額です。
例えば次のものが仮想通貨取引では費用に当たります。
- 出金手数料
- 取引手数料
- 仮想通貨投資のコンサルティング費用
- 仮想通貨関連のセミナー代
- インターネット通信料
仮想通貨取引以外でかかった費用を必要経費として計算すれば、所得控除を受けることができるため、まずは経費計算をしておきましょう。
別の仮想通貨と損益通算する
節税対策として、別の仮想通貨と損益通算する方法もあります。
仮想通貨は雑所得として計算されますが、同じ仮想通貨内であれば損益通算することが可能です。
損益通算とは、一定期間内の所得の損益を相殺することです。
例えばビットコインで50万円の所得が出て、イーサリアムで10万円の所得が出た場合、損益通算をすることで所得を40万円に合算することが可能です。
また損益通算は3年間分の利益と損失を合算できるため、1年目に30万円の損失が出た場合に確定申告を行っておけば、二年目に50万円稼ぐと二年目の所得は20万円になります。
そのため仮想通貨取引の確定申告はたとえ一年間の所得がマイナスの場合や20万円以下だとしても、損益通算を行っておくことで翌年以降の節税対策になります。
投資を長く続けていくならば、毎年確定申告を行いましょう。
株式取引や国内FXの利益とは損益通算できない
株や国内FXも雑所得として分類されますが、「申告分離課税」に含まれるため損益通算が出来ません。
投資をしている人であれば株やFXをしている人も多いと思いますが、仮想通貨で30万円負けたからと言って、50万所得を得た株取引と合算させることは不可能です。
ただし、仮想通貨は申告分離課税に含まれないアフィリエイト収入などの雑所得とは損益通算することが可能です。
海外のFXの損失と相殺
国内のFX取引は申告分離課税と前述しましたが、海外のFX業者は国内FXと違って「総合課税」です。
そのため、仮想通貨取引で得た所得と損益通算することができます。
例えば仮想通貨で50万円の利益を出し、海外FXの損失が20万円ならば、雑所得は30万円となります。
他の投資と損益通算することによって、節税が可能になるケースは多いので、まずは損益通算できないか確認してみましょう。
仮想通貨の確定申告に関するよくある質問
仮想通貨の確定申告に関するよくある質問と回答を紹介します。
- 仮想通貨の利益は何円から確定申告が必要?
- 仮想通貨の確定申告は難しい?
- 仮想通貨の確定申告を楽にする方法は?
- 仮想通貨で利益が出たのに確定申告しないとどうなる?
仮想通貨の利益は何円から確定申告が必要?
日本の税法では、仮想通貨の利益が年間で合計して20万円以上ある場合、確定申告が必要とされています。
暗号資産(仮想通貨)による所得は原則として雑所得に分類され、1ヶ所から給与をもらっている会社員の場合は20万円から確定申告が必要です。
ただし、医療費控除を利用する場合や給与以外の収入で確定申告を行う際に関しては、仮想通貨の所得が20万円以下であっても申告書に記載する必要が出てきますので注意しましょう。
仮想通貨の確定申告は難しい?
仮想通貨の取引は複数の取引所で行われることが一般的なので、各取引所から取引履歴を取得し、正確に管理する必要があります。
また取引所の取引履歴の形式やデータの取得方法が異なる場合もあり、それらを統合することが難しいことがあります。
さらに仮想通貨の評価方法は複数存在し、価格指標や取引所の価格、特定の日時の価格など、さまざまな方法があります。
適切な評価方法を選択し、それに基づいて利益や損失を計算する必要があります。
仮想通貨の確定申告を楽にする方法は?
仮想通貨の確定申告では、複雑な損益計算を自動化してくれる税金計算ツールを活用するのがおすすめです。
仮想通貨の確定申告におすすめの税金計算ツールには下記のようなものがあります。
- クリプタクト(Cryptact)
- ジータックス(Gtax)
- クリプトリンク(CryptoLinC)
仮想通貨で利益が出たのに確定申告しないとどうなる?
仮想通貨で一定の利益が出たにも関わらず確定申告を行わない場合、税務当局による税務調査や罰則の対象となる可能性があります。
具体的には延滞税や加算税などの、税務上のペナルティが発生します。
延滞税は、確定申告の締め切り日までに確定申告を行わず、税金の納付が間に合わなかった時に発生するペナルティ。
加算税は、確定申告や納税が正しく行われなかったときに課せられるペナルティのことを指します。
仮想通貨取引は所得20万円以上で確定申告をする必要がある
仮想通貨取引は会社員の場合、所得が20万円以上で確定申告をしなければなりません。
所得は利益から費用を引いた金額なので、費用を経費計上すると確定申告をしなくてもよい可能性もあります。
しかし、仮想通貨取引は仮想通貨を売却したとき以外にも、仮想通貨で決済を行った場合も所得が発生するため、間違えると延滞税が課税されることもあります。
申告額にミスがないように気を付けて、できるだけ早めに申告しておきましょう。